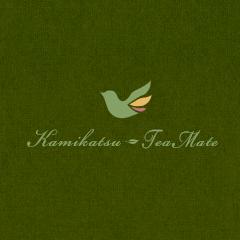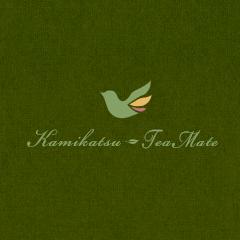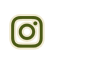皆さんこんにちは!
Kamikatsu-TeaMateの更新担当の中西です!
さて今日は
未来に繋ぐ阿波晩茶〜課題〜
ということで、現在、上勝町で抱えている課題について深く考えていきたいと思います。
上勝町(徳島県)は、四国山地の中腹に位置する自然豊かな町で、「ゼロ・ウェイスト宣言」などの環境への取り組みで国内外に知られています。しかし、その美しい風景とは裏腹に、深刻な過疎化と高齢化の波に直面しており、特に地域の基幹産業であるお茶農業にも大きな影響を与えています。

◆ 上勝町の人口動態と高齢化の現状
2025年現在、上勝町の人口はわずか1,300人ほど。そのうち高齢者(65歳以上)の割合は約53%と、全国平均(約29%)を大きく上回っています。若年層の流出が続いており、町内に定住する働き手が極端に不足しているのが現状です。
◆ お茶農家の人手不足の実態
上勝町のお茶産業は古くから続く伝統産業で、山間の段々畑で丁寧に手摘みされる「阿波晩茶(あわばんちゃ)」が特に有名です。しかし現在、その伝統を支える担い手が急速に減少しています。
◉ 主な課題
-
高齢農家の増加
茶農家の多くは70代以上で、体力的に厳しい作業を継続するのが困難になってきています。
-
後継者不足
地元の若者は都市部に移住する傾向が強く、農業に興味を持つ人材が町内外でも極めて少ないのが現状です。
-
収穫期の労働力確保の困難
お茶の収穫は一斉に集中するため、短期間に多くの人手が必要になりますが、その人手が確保できず、収穫をあきらめる農家も出てきています。
◆ 晩茶生産の現状と減少の実態
◉ 生産農家の高齢化
上勝町で晩茶を生産している農家は、2020年代には約30軒程度でしたが、現在(2025年)では20軒を下回るとも言われています。しかも、その多くが70代から80代の高齢者であり、作業の継続が年々難しくなってきています。
晩茶の製造工程は非常に手間がかかるため、若く体力のある労働力が必要ですが、以下の理由から若手の参入が難しいのが現実です:
◉ 生産量の減少
農林水産省や地元組合によると、阿波晩茶の生産量は2000年代前半に比べて半減しているとの報告もあります。主に以下の要因が関係しています:
-
労働力不足による作付け面積の縮小
-
発酵樽などの設備を管理・維持する体制の弱体化
-
天候不順や高温化による品質への影響
◆ 高齢化のもたらす課題
高齢化がもたらす影響は、単なる生産量の減少にとどまりません。
| 課題 |
詳細 |
| 技術継承の危機 |
晩茶づくりには熟練した感覚と知識が不可欠。教える相手がいなければ技術が途絶える。 |
| 地域経済の縮小 |
晩茶は観光土産や特産品としても重要。生産減少により町の収入源も細る。 |
| 文化的価値の喪失 |
晩茶は単なる農産物ではなく、上勝町の「生活文化」。継承されなければ文化ごと失われる。 |
◆ 自家用茶としての晩茶文化
上勝町の晩茶づくりは、もともと各家庭で自家用として作る伝統から始まったものです。夏になると家族総出で茶葉を摘み、釜で茹で、漬け込み・発酵・天日干しまでを行うというのが上勝の暮らしの一部でした。
このように「商品」ではなく「生活の一部」として生まれ育った晩茶は、経済的利益よりも文化的・精神的価値に重きが置かれてきました。しかしそのことが現代においては、深刻な後継者不足の一因になっています。
◆ 商業化の壁:収益性の低さ
晩茶は手間暇のかかる製法であるにも関わらず、他の一般的なお茶と比べて生産量が限られ、流通量も少ないため、販売による収益は極めて限定的です。
◉ 主な要因
-
収穫が年に一度(夏のみ)
-
乳酸発酵という特殊製法
-
販路が限られている
結果として、副収入や趣味としては成立しても、専業として生活を支えるのは困難という認識が根強くあります。
◆ 後継者が育たない背景
◉ 1. 収益面での魅力不足
若者が「この仕事で生きていける」という明確な収入モデルが存在しないため、他の仕事を選ばざるを得ない状況が続いています。特に家族を養う世代にとって、年に一度の収穫で得られる収入では生活が成り立たないという厳しい現実があります。
◉ 2. 技術の属人化
晩茶づくりは、各家庭ごとに異なる独自のレシピや工程があり、「教わる」というより「見て覚える」職人的な文化です。このため、体系的に学べる環境が整っておらず、技術継承が非常に困難になっています。
◉ 3. 地域の人口構成と教育機会の少なさ
上勝町の若年層人口は極端に少なく、地元の中学校卒業後は多くの子どもたちが町外の高校・大学に進学します。そのまま都市部に就職・定住するケースが大半で、UターンやIターンによる定着が極めて稀です。
阿波晩茶はオンラインでもご購入できます♪
オンラインショップ